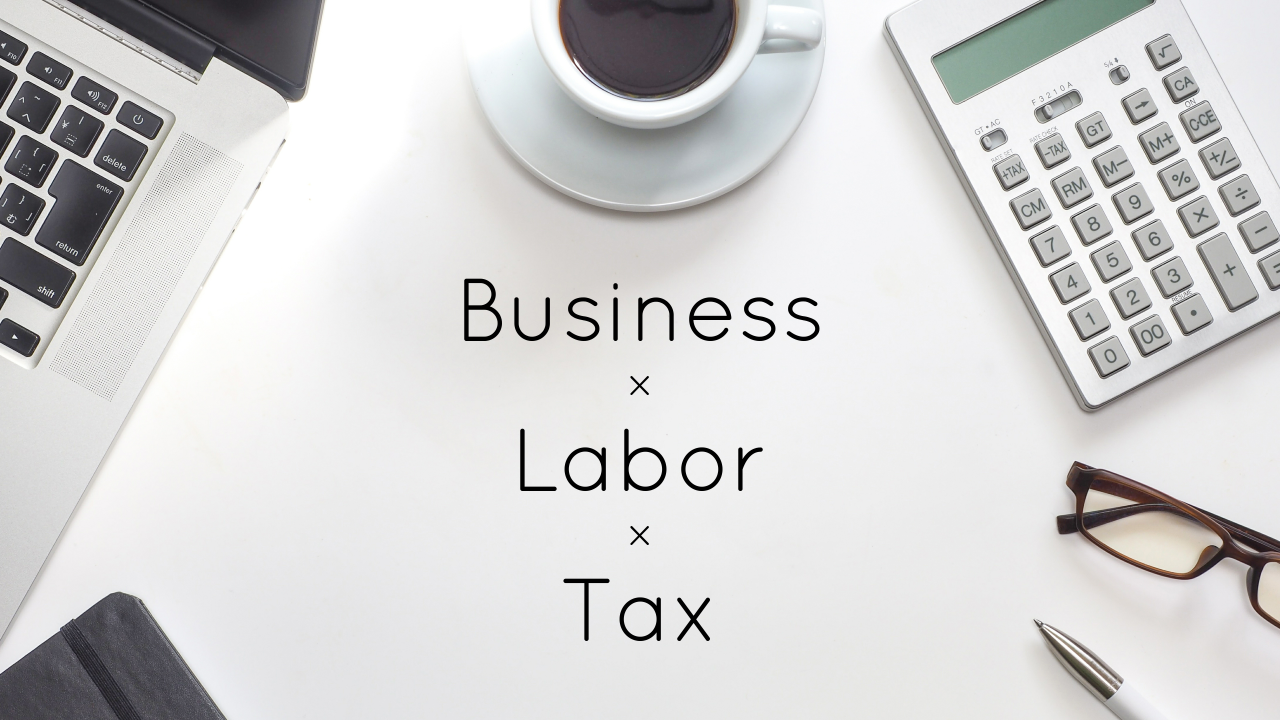「扶養」には、税法上(所得税)の扶養と社会保険上の扶養の2つの種類があり、それぞれ扶養の対象となる子供の年齢や収入の金額などについて違いがあります。
このページでは、子供に関する扶養に絞ってくわしく説明します。
所得税法上の扶養
次の4つの要件のすべてに当てはまる人を税法上において「扶養親族」といいます。(所得税法第84条)
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)であること
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
この扶養親族である子供について所得税の控除を受けるためには、子供の年齢や収入が影響してきます。
年齢による制限と控除の金額
所得税の控除を受けられる対象となる子供は、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上に限られます。つまり16歳未満の子供は、他の条件を満たしていても所得控除を受けられる扶養に該当することはありません。
その年の12月31日において16歳以上の扶養親族である子供であれば、年齢の上限はありませんので、扶養控除を受けることができます。所得から控除できる金額は、次のように子供の年齢によって異なります。
| 年齢による区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 16歳未満 | 0円 | |
| 19歳以上23歳未満(特定扶養親族) | 63万円 | |
| 24歳以上(一般の控除対象扶養親族) | 38万円 | |
なお、19歳以上23歳未満の扶養親族を「特定扶養親族」といいます。この特定扶養親族は、大学生であるか否かは問わないので、学校に通っていなくても扶養者が63万円の所得控除を受けることができます。
収入による制限:103万円の壁
子供が16歳以上であれば扶養控除の対象となりますが、上記の扶養控除を受けるには、子供の収入に制限があります。
扶養親族の収入については、「その年の合計所得金額が48万円以下であること」が条件となっています。
合計所得金額とは、アルバイトによる給与所得の場合、収入金額から給与所得控除額を差し引いた後の金額をいいます。
つまり、給与による収入が年間103万円を超えると、その年は親の扶養から外れることになります。
なお、アルバイト以外の収入、例えばYouTubeの収益やアフィリエイト収入、ハンドメイド品の販売やセドリによる収入などの事業所得や雑所得があった場合には、
売上-経費=合計所得金額
となるので、年間の売上から経費を差し引いた金額が48万円を超えると、所得税法上の扶養から外れることになります。
子供の合計所得金額が48万円を超えると、親の手取り額が減る(所得税額が増える)だけでなく、子供にも所得税がかかることになります。
社会保険上の扶養
親が会社の社会保険に加入する場合、その家族を扶養に入れることができますが、社会保険上の扶養には「厚生年金」と「健康保険」の2つの制度があり、それぞれ扶養の対象が異なります。
子供は厚生年金の扶養対象外
厚生年金の被扶養者の対象者は「20歳以上60歳未満の配偶者」のみなので、子供が親の扶養に入ることはできません。
子が20歳以上になったら、その子供本人が国民年金保険に加入し、ご自身で保険料を納めることになります。
健康保険の扶養の条件
健康保険については、働き方や収入金額による扶養の条件があります。
年齢による制限はない
健康保険の場合、子供に関して年齢の制限はないので、何歳でも扶養に入ることができます。
ここで重要なのが、扶養に入る条件として所得税同様、次のような収入の壁があります。
収入による制限:約106万(月88,000円)の壁
いわゆるアルバイトやパートタイマーのような、労働日数と労働時間が通常の労働者の3/4未満である労働者のことを「短時間労働者」といいます。
令和4年10月より、従業員数101人以上の企業で働く短時間労働者は、次の4つの条件をすべて満たす場合、社会保険に加入しなければなりません。※令和6年10月からは51人以上の企業に拡大されます。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上
- 学生でないこと
この短時間労働者の社会保険加入の制度は学生は対象としていないため、子供が学生である場合は後述する130万円未満の収入であれば、親の扶養に入ることができます。
一方で学校を卒業した子供が、1月あたり88,000円以上稼ぐような短時間労働者の社会保険加入の条件に当てはまる働き方をすると、その子供本人が社会保険に加入することになるので、親の扶養から外れます。
収入による制限:130万円の壁
(※子供が障害者の場合、130万円は180万円になります。)
このいわゆる「130万円の壁」と呼ばれる社会保険の扶養は、学生であるか否かを問わず、子供の年間収入が130万円未満であり、かつ親の年間収入の1/2未満または親の年間収入を上回らなければ、被扶養者として認定されます。この130万円という金額は、所得税と異なり、今後1年間の見込みの収入で判断します。
130万円以上の収入が見込まれる場合は、親が加入する健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入することになり、子供の収入に応じた国民健康保険料を納付しなければなりません。

親がフリーランス・個人事業主の場合
ここまで、親が会社の社会保険に加入するケースで説明しましたが、子供を扶養する親がフリーランスや個人事業主などの自営業だったり、社会保険に加入しない非適用業種の会社で勤務している場合は、「国民年金保険」と「国民健康保険」に加入することになります。この2つの制度にはそもそも扶養の制度がありませんので、それぞれの公的年金制度と健康保険組合に加入することになります。
ただし、健康保険について職種による健康保険組合に加入する場合には、被保険者の家族も加入できることがあります。健康保険組合によって加入の対象・条件が異なりますので、それぞれの健康保険組合にご確認ください。