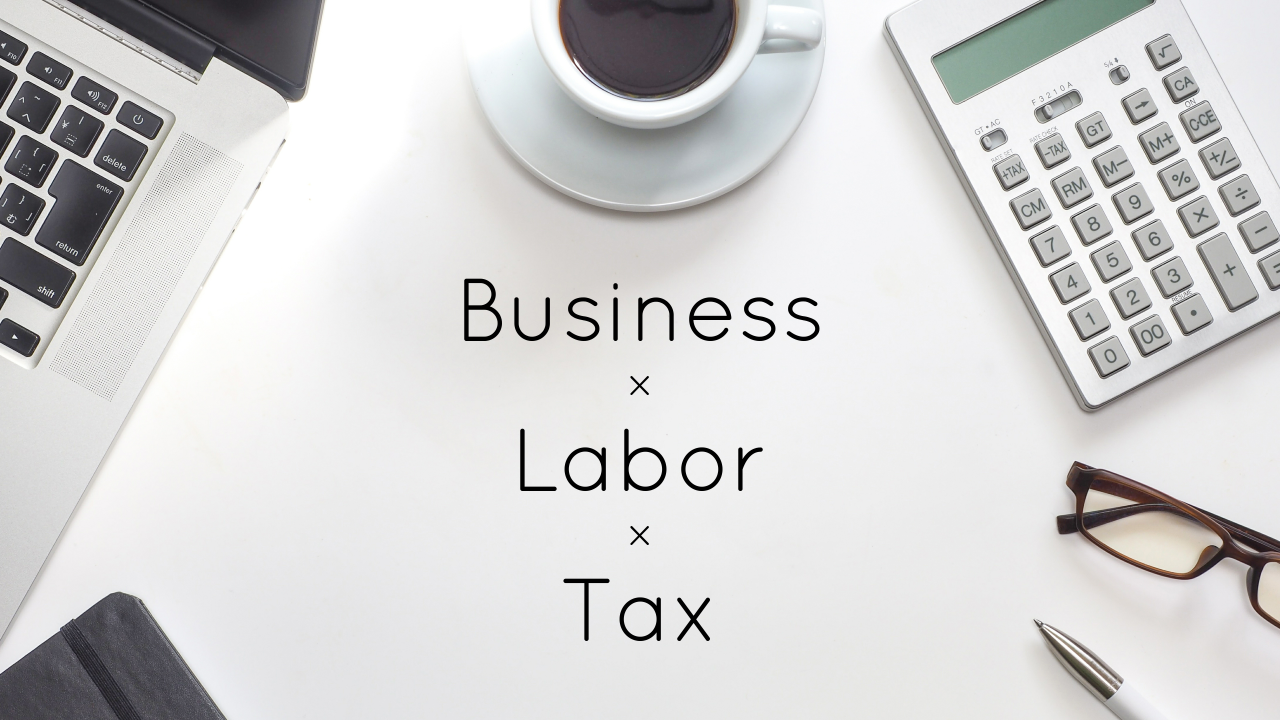年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、労働者が取得する休日以外に、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日をいいます。
労働基準法第39条で労働者に認められた権利ですので、就業規則等に規定がなくても、使用者は労働者に対し定められた年次有給休暇を与えなければいけません。
有給休暇付与の条件
有給休暇を取得するためには、次の2つの要件(継続勤務・出勤率)を満たす必要があります。
継続勤務要件
・雇い入れの日(入社日)から6か月経過していること
継続勤務は、在籍している期間で判断されますので、休職や長期の欠勤、産休・育休の期間も含まれます。
また、アルバイトやパートタイム労働者から正社員登用した場合や定年退職後に期間を開けず嘱託社員として再雇用された場合なども、変更前の身分としての雇用日から起算します。
出勤率要件
・その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
「出勤日」とは、所定休日を除く、出勤をした日または出勤をしたとみなされる日です。
- 実際に出勤をした日(遅刻・早退した日を含む)
- 有給休暇の取得日
- 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
- 産休・育休・介護休業期間
- 台風や火災などの天災事変による休業日
- 雇用主側の理由のよる休業日
※所定休日に休日出勤した場合は、出勤日に含まれません。
「全労働日」とは、その会社の就業規則等で労働の義務があると定められた日をいいます。
※全労働日から除かれるもの
- 所定休日による休日出勤日
- 台風や火災などの天災事変による休業日
- 雇用主側の理由のよる休業日
有給休暇の付与日数
使用者は上記の要件を満たす労働者に対し、労働者の雇用形態や状況、勤続勤務年数に応じて定められた日数の有給休暇を与えることが義務付けられています。
通常の労働者(正社員など)
週の所定労働日数が5日以上又は週の所定労働時間が30時間以上の労働者
| 勤務 年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 以上 |
| 付与 日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
短時間労働者(アルバイト・パートタイム労働者など)
・週の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
・年の所定労働日数が216日以下である(週単位で所定労働日数が定められていない場合)
| 週の所定 労働日数 | 年間の所定 労働日数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 | 2年 6ヶ月 | 3年 6ヶ月 | 4年 6ヶ月 | 5年 6ヶ月 | 6年6ヶ月 以上 |
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※年の途中で労働日数の雇用契約が変更された場合、付与日時点の所定労働日数で計算します。
※4月15日に採用した場合、10月15日に最初の有給休暇が与えられ、その後毎年10月15日に上記の表に該当する日数が付与されます。給料の締日は関係なく、雇用日から起算します。
有給休暇の有効期限
有給休暇の時効は、2年です。
付与日から2年間請求することが可能ですが、2年を超えて消化されなかった有給休暇は消滅します。
有給休暇の基準日を統一する方法
有給休暇の基準日とは、有給休暇が付与される日のことを指します。
原則として、雇用開始日が基準とされていますが、中途採用者が多い企業などの場合、労働者によって有給休暇の発生日がそれぞれ異なると、その管理が煩雑になってきます。
そこで、基準日を統一して管理する方法が認められています。統一日を決めて全社員一斉に年次有給休暇を付与します。(基準日を年間に2~3回設定する方法もあります。)
この方法を採用した場合、勤務期間を切り捨てたり四捨五入することは認められていません。